


・ 自分に適ったものを見つけること、これ何事にも共通である。
サプリメント 然り。
さて、今回は、ステッパーを使ってトレーニングしたら、体力が約3倍になった実録をご紹介しよう。
・ まず以下のグラフをご覧下さい。
縦軸は、脈拍数毎分約120を維持しながら、ステッパーを15分間で踏んだ時の回数(カウント数・・・両足1回ずつ2ステップで1カウント)である。
横軸は、2002年3月28日から2004年4月16日までの日付(時間軸)である。
( トレーニングした人は : 男性 スタートした年齢 60歳− グラフの終わりの年齢 62歳 )
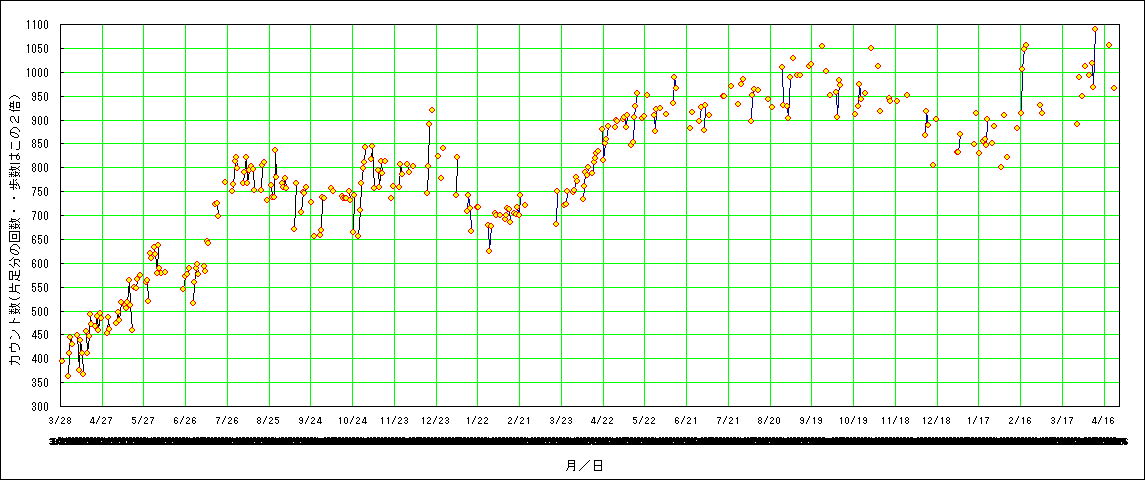
スタートした時、15分間に踏めた回数は 350−400 回(両足1回ずつ踏で1回と数える) であった。
2年間のトレーニングの結果、踏める回数が 950−1100 回 になった。
・ どんな意味での体力か
エアロビック(有酸素)な負荷(運動の激しさ)の範囲で、実行できる運動量で計測した 体力 である。
これは、心肺機能、と筋肉の能力の総合である。
・ エアロビック運動とは(厳密な解説ではなく、大雑把な把握として)
筋肉は使い始めるとき、一時的に酸素を使わずに運動が行われる。これをアネロビック(無酸素)運動といい、アデノシン3リン酸がアデノシン2リン酸という物質に変化する
ことによりエネギーを放出することによる。アデノシン2リン酸はエネルギーを逆に供給するとアデノシン3リン酸に戻る。
続いて筋肉中のブドウ糖、脂肪をエネルギー源として運動が行われる。(脂肪は使われにくく、一定の比率以下にとどまる。)
ブドウ糖と脂肪は酸素を消費しながらエネルギー源となるのであるが、供給される酸素量が運動で消費される量をまかなえる状態にあることをエアロビックな状態であるという。
筋肉で使用される酸素は、血液から供給されるのであるから、血液を送る心臓と、血液中の炭酸ガスを排出し血液に酸素を取り込む肺の能力との総合ということになる。
さらに、筋肉はエアロビックな状態で運動を行う(訓練する)と、エアロビックの状態での運動を一層よくできるようになる。つまりより負荷の大きい運動をエアロビッグな状態で
行うことができるようになる。これが筋肉のエアロビック・トレーニングである。
エアロビックの状態では使われたブドウ糖と脂肪のほとんどが炭酸ガスと水になるが、運動量が大きくなるとエアロビッグの状態を保てなくなり、ブドウ糖と脂肪は炭酸ガスと
水になるまで分解されず、乳酸等の中間物質が産生される。これが筋肉中にたまると、筋肉の疲れ、凝り等の原因となる。
・ 運動がエアロビックな状態で行われているか否かの判定
運動量は、心拍と関係があることはご存じの通りである。軽い運動では脈拍はあまり増えないが、激しい運動をすると、脈拍数が増加する。つまり、脈拍すうが運動量の
目安になる。
運動がエアロビックである脈拍数の上限値は、およそ
エアロビックな状態で行われる脈拍の上限値 = 180−年齢
であることが知られている。
(東北大学大学院工学研究科機械工学専攻修士の学生さんが、これに関係する研究を行ったが、その結果は上の式と一致していた。)
・ グラフの解説
トレーニングをした人は60歳〜 ・・・・・ エアロビックな状態の運動をする心拍数の上限 180 − 60 = 120
使用したステッパー ・・・・・ 前半はオムロン製、後半は踏むと発電できるように改造したもの(機械間差がないよう調整)
脈拍の計測機 ・・・・・ キャットアイ製心拍計(センサーを耳たぶを挟んで取り付ける方式)
脈拍のコントロール ・・・・・ ステッパーを踏む速度でコントロールする
トレーニングの内容 ・・・・・
1.ウォーミングアップ 脈拍 90−100程度で10分間 程度
2.トレーニング(計測) 脈拍 120 (ぴったり120を保てない。ねらい値)で15分間 ・・・上記グラフの値がその計測結果である。
3.クーリングダウン 脈拍を順次下げて 90 位になるまで。 約10分間
結果 : エアロビックな状態で運動できる負荷の値が、350〜400 回/15分間 から 950〜1100 回/15分間になった。
「心肺機能と筋力が向上したので、他の運動もできるようになった」 とのこと。
皆さんも試してはいかがですか!
